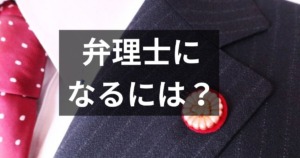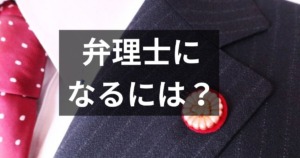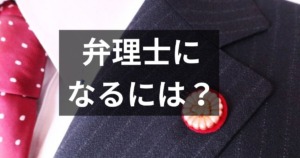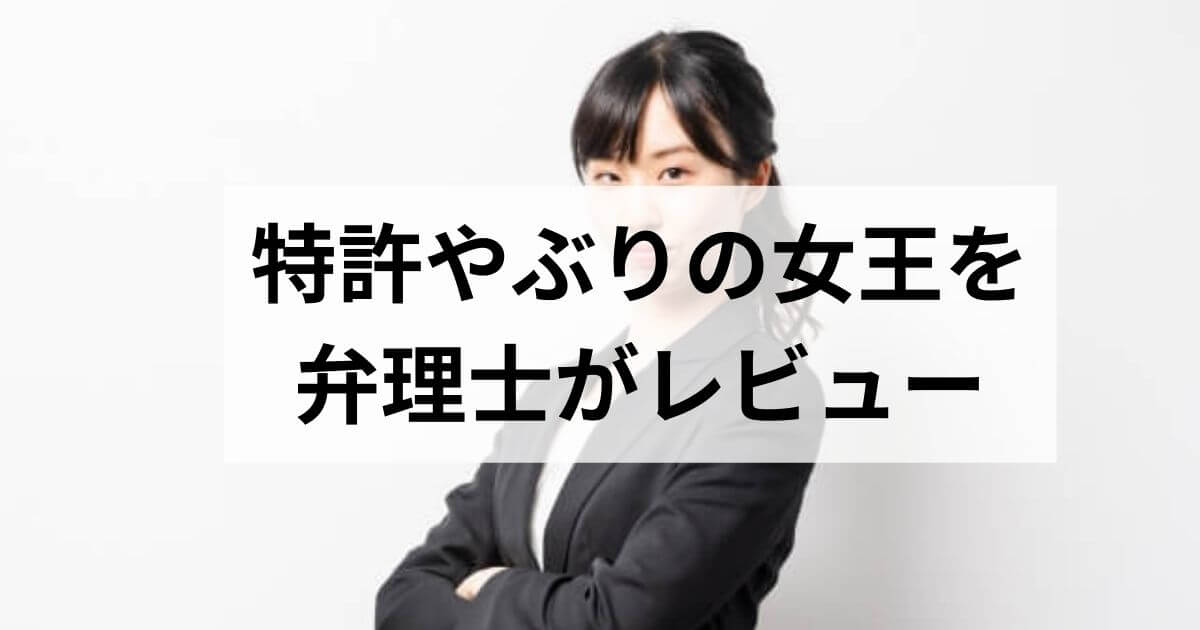特許を題材にしたミステリーが第20回「このミステリーがすごい」大賞を受賞しました。
しかも作者の南原詠氏は企業に勤務する現役弁理士です。
「特許らいふ」としては本書をレビューしないわけにはいきません。
かなり専門的な話も含まれていますので、弁理士の視点からじっくり検討していきます。
「特許やぶりの女王」のあらすじ

特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来
まず「特許やぶりの女王」の出版社紹介文を引用します。
第20回『このミステリーがすごい!』大賞受賞作は、現役弁理士が描く企業ミステリーです!
特許権をタテに企業から巨額の賠償金をせしめていた凄腕の女性弁理士・大鳳未来が、「特許侵害を警告された企業を守る」ことを専門とする特許法律事務所を立ち上げた。
今回のクライアントは、映像技術の特許権侵害を警告され活動停止を迫られる人気VTuber・天ノ川トリィ。
未来はさまざまな企業の思惑が絡んでいることに気付き、そして、いちかばちかの秘策に……!
弁理士が主人公で、特許をミステリー仕立てにした小説というのが斬新ですが、それだけではありません。
VTuber(バーチャルYouTuber)、5G(第5世代移動通信システム)といった旬なカルチャーやテクノロジーを題材にしていることも注目ポイントです。
フィクションらしく現実離れした展開がありつつも、数多くの専門知識をベースに作られており、知財の世界を覗いてみたい方は一読してみてください。
しかし、中には「難しそう」と躊躇してしまう方もいるかもしれません。
実際に「このミス」大賞の選考では、話は面白いが、法律の説明が難しいと選者から指摘されています。
講評を受けて出版前に改稿された結果、難しさは緩和されたようで、それなりに読みやすい仕上がりになっていると思います。
「特許やぶりの女王」の解説
「特許やぶりの女王」は前提知識なしでも読めますが、ストーリーをテンポよく進めるためか、専門用語の説明などはあっさりとしています。
もっと知財を知りたい方のために、小説内で触れられなかった周辺知識について解説していきます。
- 以下、ネタバレが少なくなるように配慮していますが、読了後に読まれることをおすすめします。
発明の新規性・進歩性
知財の仕事をしていると「こんな簡単な物が特許になるの?」という特許をよく見かけます。
作中でシンプルな特許(電源を入れるとテレビ番組より先にブラウザが立ち上がるテレビ)について議論しているシーンから引用します。
新しければ特許されます。ただし、世間一般の基準での新しさと特許庁の審査官にとっての「新しさ」は、異次元レベルで異なります。新規性といいます。
説明されているとおり「新規性」の水準は意外と低く、既存の2つの発明を組み合わせただけでも新しいとみなされます。
作中では触れられていませんが、実は特許を取るためには新規性だけでなく、一段階上の「進歩性」も必要です。
新しいだけでなく、既存の発明に対して技術的な効果がなければ進歩性をクリアできません。
進歩性の判断基準は、時代や担当の審査官などによってバラツキがあるのが実情です。
厳しいときは厳しいですが、易しいときには何でも登録されてしまうような錯覚を覚えるほどです。
このような事情から、ときに「こんな物が」という特許が成立してしまうことがあります。
侵害者への差止請求



皆川社長、たとえ侵害でも、あなたに認められる権利はテレビの廃棄と工場設備の取り除きまで。
侵害品のテレビを持ち出そうとした特許権者の皆川に対して弁理士・大鳳未来が放ったセリフです。
侵害品を自社製品に作り変えて販売する魂胆ですが、そのような行為は法律上許されません。
専門的な話になりますが、特許法100条に特許権者ができる行為が規定されています。
第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
細かい部分はあまり気にせず、赤字に注目してください。
テレビの廃棄とは「侵害の停止」を請求すること、工場設備の取り除きとは「侵害の行為に供した設備の除却」を請求することを指しています。
特許権者がこれらの請求をできる権利を差止請求権と呼びます。
なお、本書に書かれているように、差止請求権とセットで損害賠償請求権(民法709条)が行使されるのが普通です。
パテント・トロール



業界外の人には聞き慣れないパテント・トロールという言葉が出てきます。
作中では次のように端的に説明されています。
パテント・トロールって、自分では事業をする気のない製品の特許を取得し、特許侵害だと他の企業にぶつけて金をせびる組織だよな。
トロールとは、北欧の神話に登場する妖精(というよりは醜く狂暴な怪物)で、英語圏では厄介者を指す言葉として使われるそうです。
このパテント・トロールですが、日本よりもアメリカでの被害が圧倒的に多いです。
アメリカでパテント・トロールが多い理由として、
- アメリカの市場規模が大きいこと
- 訴訟での特許権者の勝率が高いこと(ただし時代にもよります)
- アメリカでは損害額の3倍までの賠償を請求できること(いわゆる3倍賠償)
が考えられます。
しかし、日本企業であってもパテント・トロールの標的になる可能性は十分あります。
本書で触れられていますが、米国の個人発明家・コイル氏が任天堂とセガを訴えたコイル事件が代表的です。
コイル氏の特許の内容は、音の信号を取り込んでカラーテレビ信号を作り出すものでした。
本来、インテリアの用途を意図した特許であり、ゲーム機とは関係なさそうですが、色々と理屈をこねて攻撃された結果、任天堂は相当額で和解し、セガは敗訴して多額の賠償金を支払うはめになりました。
他にも日本企業が狙われた事例があり、海外でビジネスする日本企業にとってパテント・トロールは脅威となっています。
登録商標
登録商標とは、特許庁によって独占が認められた商標のことです。
作中では初音ミク(権利者:クリプトン・フューチャー・メディア)、ボーカロイド(権利者:ヤマハ)といった登録商標が挙げられています。
ボーカロイドのように一般名称と思いきや実は登録商標だったという例は、セロテープ、宅急便、万歩計など多数あります。
ちなみに登録商標を調べるには、特許庁サイトのJ-PlatPatを使うのが簡単です。
商標の使用
他にも商標について気になるセリフがあります。
(初音ミクやボーカロイドは)一般名称ではありませんので、使用はご注意ください。
この「使用」とはどのような行為を指すのか分かりますか?
単に商標を声に出して言うとか、ブログに書くだけでは商標の「使用」にはなりません。
登録商標には特定の商品や役務(サービス)が指定されており、これらとの関係で用いる行為が「使用」です。
「使用」に該当する具体的な行為は商標法2条3項に規定されています。
条文の一部を見てみましょう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為(以下略)
※条文中の「標章」は商標と同じ意味です。
条文には難しい表現が含まれているので、身近なところで「使用」の例を挙げてみます。
- ベンツのエンブレムを販売用の車に付ける
- サイゼリヤと書かれたグラスを客に使わせる
何となくイメージできたでしょうか?
それでは、初音ミクとボーカロイドの話に戻って、「使用」を考えてみます。
登録商標「ボーカロイド」の指定商品に「電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル」があります。
商品の音楽ファイルに「ボーカロイド」という名前を付けてしまうと、登録商標の「使用」に該当し、商標権侵害が成立します。
「使用はご注意ください」というセリフは、このような侵害行為をしないようにという親切な忠告です。
弁理士はAIに代替される?
オックスフォード大と野村総合研究所の研究によれば、弁理士業が二十年以内にAIに代替される可能性は九十二・一パーセントとか
依頼人の棚町が大鳳弁理士を挑発したシーンです。
業界人にとって聞き捨てならないセリフですが、小説では受け流されて深堀りされることはありませんでした。
一弁理士としては強く反論しておきたいところです。
下記の記事に反論を書いていますので、弁理士の将来性が気になる方はぜひどうぞ。
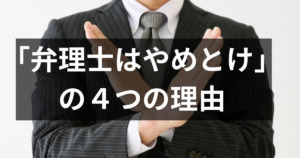
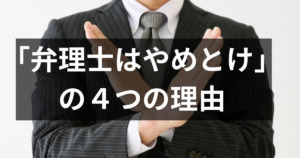
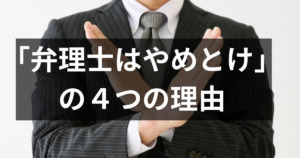
専用実施権
特許権でなく、専用実施権の侵害という設定がストーリー上の大きなポイントですが、業界外の方には少し理解しづらかったかもしれません。
特許権と実施権(ライセンス)の関係について少し掘り下げてみましょう。
まず、特許権とは発明を独占排他的に実施できる権利です。
独占排他的と言うと小難しく聞こえますが、要は自らが実施できるし、他人の実施を排除できるわけです。
しかし、様々な事情で他社に発明を実施させたい場合などがあり得ます。
この場合に「実施していいよ」と口約束しただけでは不安が残るので、特許権者によって実施権が設定されることになります。
実施権には、専用実施権の他に、通常実施権という種類があります。
名前のとおり、通常実施権の方が専用実施権よりも一般的な実施権です。
通常実施権は発明が実施できるだけのシンプルな権利です。
通常実施権を持っていても、特許権者による実施を禁止できません。
また、第3者が無断で発明を実施していても、通常実施権者は文句を言えません。
一方、専用実施権は本書で説明されているように、特許権者に変わって技術を独占する強力なライセンスです。
専用実施権を設定すると、特許権者であっても発明を実施することはできません。
しかも専用実施権者は第3者の実施に対して権利行使できます。
読了後の方は分かると思いますが、これらのルールがストーリー展開で重要な意味を持っています。
特許侵害の責任



VTuber・天ノ川トリィは、如月測量機器という怪しい業者から撮影システムを購入していました。
もしあなたの撮影システムが侵害品なら、如月測量機器は侵害品を売っていた業者になるわけです。責任を取らせましょう。
とのセリフがありますが、業者が雲隠れした場合に責任を取らせるのは現実的には厳しいです。
そのようなリスクを考えると、やはり仕事道具は信頼できる業者から買うべきです。
知財への意識が高い会社は、侵害事件に巻き込まれるリスクを回避するために、取引先が知財の問題を抱えていないかをチェックしています。
クレームチャート
侵害者に警告する際に同封すべき書類のクレームチャートを説明します。
クレームとは日本語で「特許請求の範囲」と呼ばれ、文章により権利範囲を規定しています。
本書に登場するクレームは、レーザーを使っていること、5Gを使っていることといった条件の組み合わせで表現されます。
これらの条件(専門的には発明特定事項と言います)をひとつずつ並べ、検討対象の製品が各条件を満たしているかどうかを丁寧に調べていきます。
その検討結果を示した書類がクレームチャートです。
権利者が何を根拠に侵害を主張しているのかを知るためにクレームチャートが必要となるわけです。
無効資料調査



特許侵害で訴えられてしまった場合に、特許を無効にするのがひとつの対抗手段です。
特許を無効するための調査が無効資料調査です。
特許は、特許庁の審査官が先行技術を調査した上で登録されますが、その判断が絶対に正しいとは言い切れません。
出願前に知られている先行技術を全て調査するのは不可能だからです。
無効資料調査では、審査官の判断を覆すためにより深く調査を行っていくことになります。
日本の特許情報はもちろん、外国の特許情報、学術論文、インターネット上の情報など、その気になれば調査範囲に限りはありません。
どこまで調べるかは案件の重大性や、目的の情報が見つかる見込みなどに応じて決めます。
調査の結果、そのものズバリの先行技術が見つかれば、本書に書かれているように大成功です。
特許に問題があったと文句をつける一番の方法は、特許出願より前に公開されていてかつ特許の内容が全部載っている文献を見つけることだ。
この場合、特許は新規性がないため無効であると主張できます。
一方、決定的な文献が見つからない場合もあり得ます。
バラバラに見つかった場合、使えはするが文句がつけにくくなる。
バラバラに見つかった場合、進歩性違反を争うことになります。
特許を無効にするためには特許庁に対して無効審判を請求するのが基本ですが、すでに訴訟中ならば訴訟の中で特許の無効を主張することもできます。
冒認(ぼうにん)出願
冒認出願とは他人の発明を無断で出願してしまうことです。
冒認出願して登録されても特許は無効です(ただし、実際に無効にするには無効審判が必要)。
問題になりやすいのは、本書のように従業者が職務として完成させた発明(職務発明と言います)を会社が出願した場合です。
原則として発明した従業者が正当な権利者であり、会社が勝手に出願すると冒認出願になります。
しかし、研究開発資金や設備の提供など会社も職務発明の完成に大きく貢献しているので、従業者が権利を独占するのは不公平です。
そこで会社が自己の権益を確保することが特許法上で認められています。
典型的には従業者に報奨金を支払い、権利を会社に譲渡させる契約を従業者と交わすことができます。
本作では会社が従業者と契約するのを怠ったことを発端として大きな問題に発展しています。
まとめ



特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来
以上、「特許やぶりの女王」の解説でした。
見返してみると、いかに大量の専門知識に作品が支えられているのかが分かりますね。
本作を機に弁理士という職業を広く知ってもらえるとうれしいです。
弁理士に興味が出てきたという方は下記の記事もどうぞ。