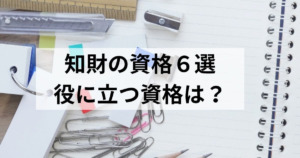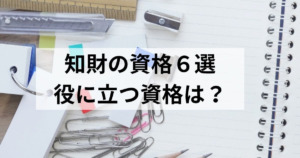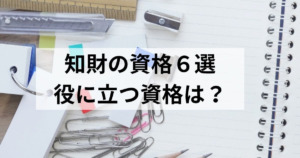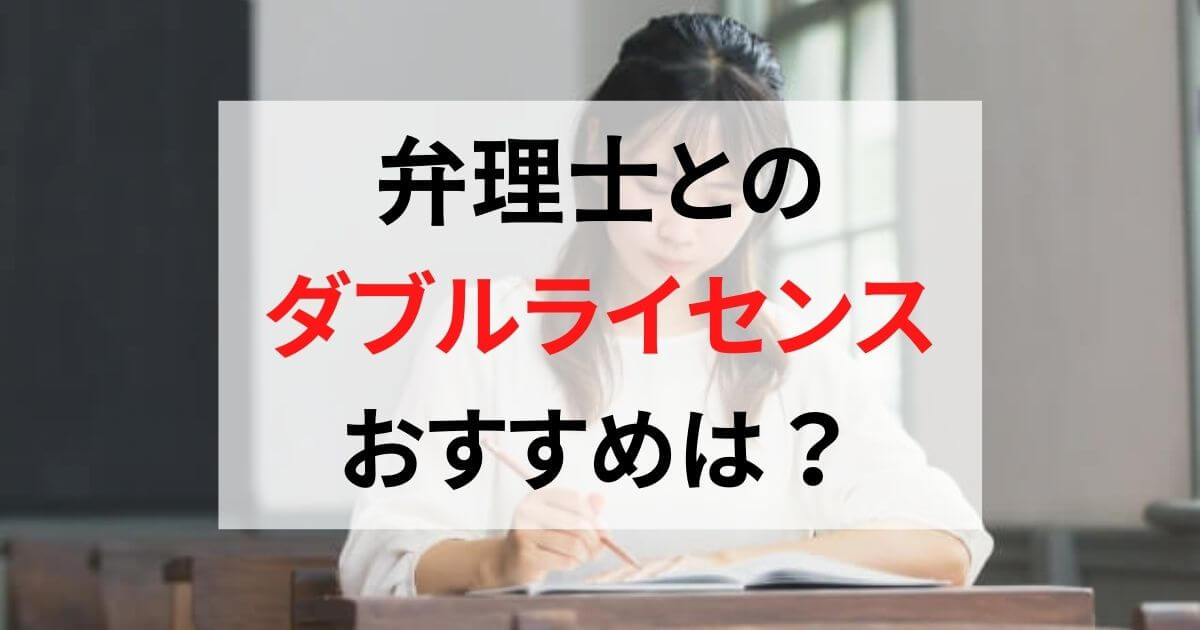弁理士の中で抜きん出た存在になるには、
・特定分野のエキスパートになる
・大手特許事務所のパートナーになる
・独立開業して事務所を拡大していく
といった手段がありますが、他資格とのダブルライセンスもそのひとつです。
このページでは、弁理士・薬剤師のイシワカが
〇ダブルライセンスのメリットとデメリット
〇どの資格を選ぶのがよいのか?
を解説していきます。
ダブルライセンスのメリット

業務の幅が広がる
弁理士という職業は専門性が高い反面、仕事の幅が狭く単調になりがちです。
特許事務所の弁理士は大半の時間を出願・中間処理に費やしていると言ってもよいでしょう。
権利化業務だけではなく、訴訟・知財コンサルなどの分野に進出しようとすると、弁理士以外の資格が大きなアピールポイントになり得ます。
希少価値が生じる
資格(特に士業)をひとつ取るだけでも苦労する人が多い中、2つ取得している人は希少な存在です。
それだけに注目を集めやすく、営業・集客で有利になります。
実際にダブルライセンスを活かしてSNSで営業活動したり、メディアから取材を受けたりしている弁理士がいます。
ダブルライセンスのデメリット



時間・費用がかかる
当然ながら2つの資格を取得するには時間と費用がかかります。
限りある時間とお金を資格試験に費やすかどうかは検討の余地があります。
例えば、資格の勉強をしなければ時間を仕事に投入して業務に習熟できますし、予備校に使うはずだった費用を自己啓発に回すことができます。
資格を活かすのが難しい
ダブルライセンスが活かせる職が、特許事務所や企業で用意されていることは稀です。
なぜなら、ダブルライセンスの人数は少ないため、求人の対象となりにくいためです。
自ら動いてポジションを作るくらいでなければダブルライセンスを活かすことは難しいでしょう。
そこまで行動できる人以外はダブルライセンスでなく、別の方面に努力を注ぐべきかもしれません。
法律系資格とのダブルライセンス
弁護士とのダブルライセンス



弁理士からのステップアップとして弁護士を目指すのは王道のひとつでしょう。
弁護士は、普通の弁理士が担当できない知財訴訟でも活躍することができます。
弁理士業務の経験を積んでいるのであれば、技術が分かっている弁護士という意味でも希少な存在になれます。
弁護士になるには法科大学院ルートと予備試験ルートの2つがあります。
法科大学院ルートは法科大学院を卒業して司法試験の受験資格を得るルート、予備試験ルートは予備試験に合格すれば司法試験を受けられるルートです。
| 法科大学院ルート | 予備試験ルート | |
| 費用 | 法科大学院の学費として200万~300万円程度 | 50万円~150万円程度 |
| 受験資格獲得までの期間 | 大卒の場合、2年または3年 | 最短で2年 |
| 難易度 | 入試の倍率による。予備試験よりは易しい | 合格率3~4%の超難関 |
どちらのルートも楽ではなく、覚悟を持って取り組む必要があります。
なお、弁護士でなくても付記弁理士となることで知財訴訟に限定的に関わることができます。
詳しくは下記の記事をどうぞ。
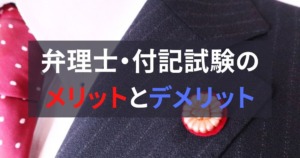
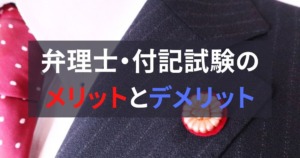
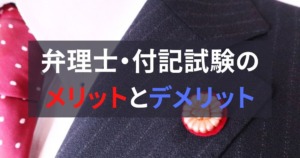
司法書士とのダブルライセンス
司法書士とは、登記(土地や不動産などの権利関係を申請すること)などの法律事務を専門とする資格です。
知的財産を扱う弁理士とは業務が大きく異なり、司法書士業務を行う上で弁理士の経験を活かせません。
したがって、弁理士と司法書士のダブルライセンスはおすすめできません。
行政書士とのダブルライセンス



行政書士は、官公署に提出する書類の作成や相談、申請手続の代理を行う職業で街の法律家とも呼ばれます。
知財とはかけ離れていますが、弁理士と行政書士のダブルライセンスは実は一考に値します。
まず、弁理士は無試験で行政書士登録でき、すぐに行政書士業務を行うことができます。
試験勉強の時間・費用がかからないのがメリットです。
実際に独立開業している弁理士で行政書士を兼業している例を見かけます。
兼業して顧客層を広げることで、仕事の増減をリスクヘッジすることができます。
社労士とのダブルライセンス
社労士(社会保険労務士)は、労働や社会保険に関する業務を行うための資格であり、知財とはあまり関係がありません。
労働関係と特許関係の業務を一気通貫して行うケースは想定しにくく、社労士とのダブルライセンスはおすすめできません。
経営系資格とのダブルライセンス
公認会計士とのダブルライセンス



公認会計士は、監査、税務、コンサルティングなど、会社の会計に関する業務を行うための資格です。
弁理士とは一見接点がなさそうですが、会計の対象となる財産には知的財産が含まれますので、実は密接に関係しています。
近年では知財の価値評価、知財コンサルティングなどへの注目が高まっており、知財業界において会計の分かる人材が求められてきています。
したがって、弁理士と公認会計士のダブルライセンスはありでしょう。
税理士とのダブルライセンス
税理士と言えば税務の専門家というイメージだと思います。
しかし、税務申告の前提として決算書や有価証券報告書が必要であり、会社経営に関する知識も要求される職業です。
税理士資格もまた、会計士のように知財の価値評価、知財コンサルティングの領域に進出する際に役立つでしょう。
中小企業診断士とのダブルライセンス
中小企業診断士は、中小企業の経営実態を診断し、経営者に適切なアドバイスする職業です。
弁理士とのダブルライセンスにより、知財を含めた総合的な経営コンサルができる存在を目指せます。
科学系資格とのダブルライセンス
技術士とのダブルライセンス



技術士は、技術コンサルタントとして指導業務などを行うための資格です。
その専門分野は21個に分かれており、技術士はその分野において高度な技能を有すると認められます。
技術士取得者は弁理士試験の選択科目が免除されることから、技術士→弁理士の順で取得する人はそれなり居るようです。
逆に弁理士→技術士の順で取得するルートがありますが、こちらは割に合わないと思います。
確かに特許業務の依頼を受ける際に技術士という権威はアピールになるかもしれません。
しかし、技術士は合格率10%程度の難関で、試験に費やす労力は相当に大きいです。
技術知識をアピールするのであれば、実務経験を積む、他資格(情報技術者など)を取る、働きながら大学に通うといった手段もあります。
これらとの比較で技術士取得にそれほどのメリットがあるようには思いません。
医師・薬剤師とのダブルライセンス
医師・薬剤師免許は、医学・薬学分野の特許業務をする上でアピールになります。
実際に医師・薬剤師を持っている弁理士はいます(ちなみに私は弁理士兼薬剤師です)。
しかし、もともと医師・薬剤師免許を持っている人が弁理士を目指すのはあり得ますが、その逆は無理があります。
医師・薬剤師免許を取得するには大学で6年もの学習が必要だからです(編入学すれば2~3年短縮可能ではありますが)。
しかもフルタイムの仕事との両立は困難なため、離職又は休職しなければならず、あまり現実的とは言えません。
知財系資格とのダブルライセンス
ダブルライセンスの本来の定義から外れるかもしれませんが、知財資格とのダブルライセンスは有力です。
代表的な知財資格に知財検定、知財翻訳検定があります。
詳しくは下記の記事をどうぞ。