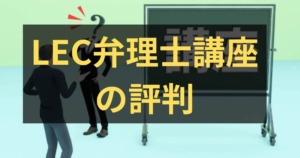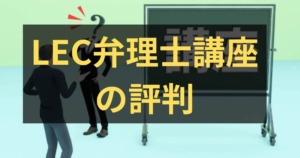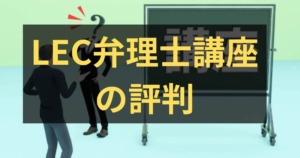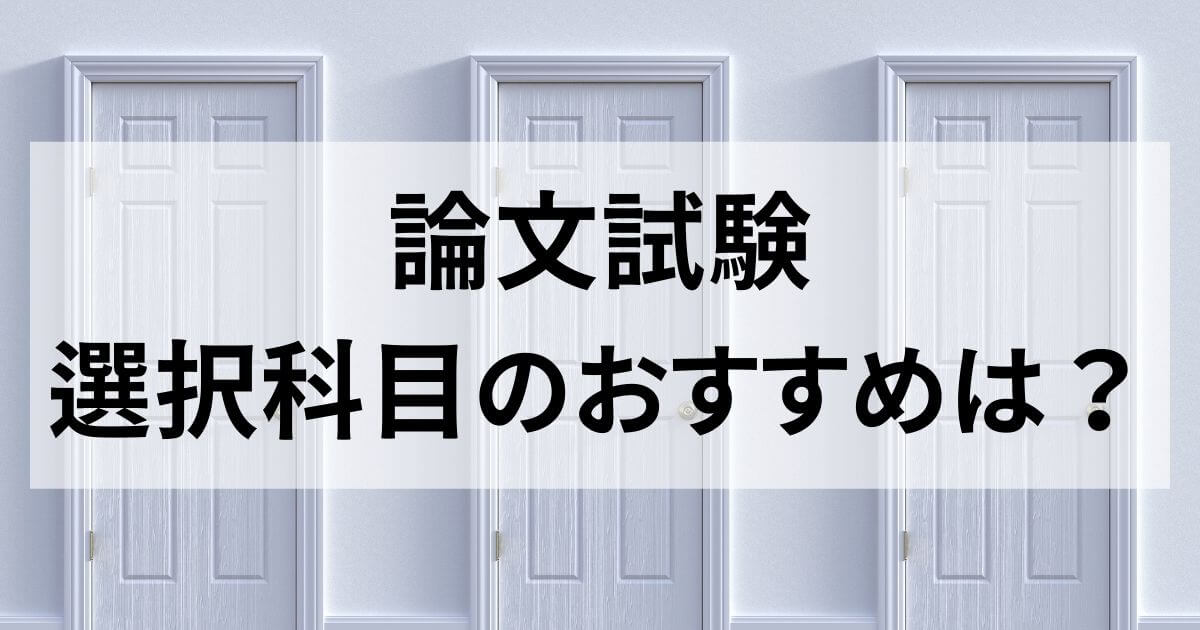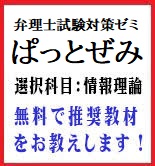この記事は、化学、機械、電気、情報処理など幅広い分野の経験がある弁理士が書いています。
弁理士試験の論文試験(選択科目)に何を選ぶか迷っていませんか?
この記事を読めば、自分に合った選択科目の選び方と勉強法が分かります。
論文式試験(選択科目)の概要
まず、選択科目の種類や試験形式などの概要について説明します。
「もう十分知っている」という方はこちらに飛んでください。
論文式試験(選択科目)の選択問題
受験願書提出時に下記の選択問題のうちの1つを選択します。後に変更はできません。
| 科目 | 選択問題 |
| 理工I(機械・応用力学) | 材料力学、流体力学、熱力学、土質工学 |
| 理工II(数学・物理) | 基礎物理学、電磁気学、回路理論 |
| 理工III(化学) | 物理化学、有機化学、無機化学 |
| 理工IV(生物) | 生物学一般、生物化学 |
| 理工V(情報) | 情報理論、計算機工学 |
| 法律(弁理士の業務に関する法律) | 民法(総則、物権、債権から出題) |
※民法の選択者には試験の際、法文集が貸与されます。
論文式試験(選択科目)の形式
いずれの選択問題も記述式ですが、正しい選択肢を選ぶ問題、空欄に語句を補充する問題が一部出されることがあります。
論文式試験(選択科目)の試験時間
1.5時間
論文式試験(選択科目)の合格基準
選択科目の合格基準は次のように規定されています。
科目の得点(素点)が満点の60%以上であること。
引用元:https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-annai.html#nagare04
選択科目では必須科目とは異なり、ボーダーラインの調整はありません。つまり絶対評価です。
問題が難しくても簡単でも確実に60%得点できる科目を選択する必要があります。
論文式試験(選択科目)の合格率・難易度
特許庁の資料からは選択科目単体での合格率は不明でしたので、科目ごとの難易度は正確には分かりませんでした。
そこで、下記の表のとおり、志願者のうちの各科目を選択した人の割合と、最終合格者のうちの各科目を選択した人の割合を比較してみました(2020年弁理士試験)。
| 志願者に占める割合 | 最終合格者に占める割合 | 増減 | |
| 理工I(機械・応用力学) | 11.7 | 9.4 | -2.3 |
| 理工II(数学・物理) | 14.6 | 17.4 | +2.8 |
| 理工III(化学) | 18.2 | 21.6 | +3.4 |
| 理工IV(生物) | 11.9 | 14.3 | +2.4 |
| 理工V(情報) | 18.4 | 19.9 | +1.5 |
| 法律(弁理士の業務に関する法律) | 25.2 | 17.4 | -7.6 |
志願者と合格者の間で割合の増減が大きくプラスなら比較的簡単な科目、逆に大きくマイナスなら難しい科目と推測されます。
まず目につくのは法律(=民法)が大きくマイナスになっていることです。
2020年だけ偶然マイナスなのかが気になったので、過去数年を調べましたが、いずれの年も大きくマイナスでした。
それ以外の科目における増減は誤差の範囲と思われます。
つまり、
- 民法の難易度は比較的高い
- その他の科目の難易度はそれほど差がない
との推測が成り立ちます。
民法は特に文系の方に人気の科目ですが、安易には選択しない方がよいかもしれません。
論文式試験(選択科目)の免除
次の3つのいずれかに該当する方は選択科目が永久免除になります。
- 論文式筆記試験選択科目合格者
一度合格すると永久免除となる点が必須科目とは異なります。
- 修士・博士・専門職学位に基づく選択科目免除資格認定を受けた方
免除を受ける人の大半が修士卒に該当するパターンです。
- 特許庁が指定する他の公的資格を有する方
対象となる公的資格は以下のとおりです。
| 技術士(ただし条件あり) |
| 一級建築士 |
| 第一、第二種電気主任技術者 |
| 薬剤師 |
| 電気通信主任技術者 |
| 情報処理安全確保支援士 |
| 応用情報技術者、又はその上位資格 |
| 司法試験合格者 |
| 司法書士 |
| 行政書士 |
新しく資格を取って免除を狙いたいなら応用情報技術者がおすすめです。
その他の資格はコスパが悪く、知財法の勉強時間を圧迫してしまうからです。
応用情報技術者の勉強については勉強法の項目で詳しく解説します。
論文式試験(選択科目)の選び方3ステップ



①専攻科目を候補にする
大学・仕事での専攻科目又はそれに近い科目がある場合は候補に挙げましょう。
専攻科目の場合、勉強時間を短縮できるのが圧倒的なメリットです。
ただし、専攻科目が実は嫌いである場合や完全に忘れてしまっている場合は別です。
目安としては、過去問の解答を自力で作れるレベルなら専攻科目を候補としてください。
②応用情報技術者を検討する
応用情報技術者はIT系資格であり、ITパスポート・基本情報技術者の上位資格です。
IT企業の社員が取得するイメージですが、学生でも合格者はそれなりにいます。
ITに抵抗がなければ、応用情報技術者を取得して選択科目免除を狙うのもひとつの手です。
実際、弁理士試験のために応用情報技術者を取得する人は少なくありません(文系の人もいます)。
応用情報技術者試験は独学でも合格可能です。
ただし、特に初学者の方は勉強の仕方を間違えて時間ロスしてしまうおそれがあるので、気を付けてください。
もし応用情報技術者試験に失敗してしまった場合は、類似科目の「計算機工学」の勉強に切り替えるのが有効です。
③選択科目を決定する
上記①、②のステップで候補となった科目からひとつを選択します。
つまり、専門科目または(応答情報技術者試験+計算機工学)となるはずです。
もし候補が0で選択できない場合は、必然的に民法となります。
民法の試験範囲と過去問を見て勉強できそうかを検討してください。
民法が難しい場合はステップ①、②に戻り、民法との比較でマシな科目がないかを再検討します。
論文式試験(選択科目)の勉強法
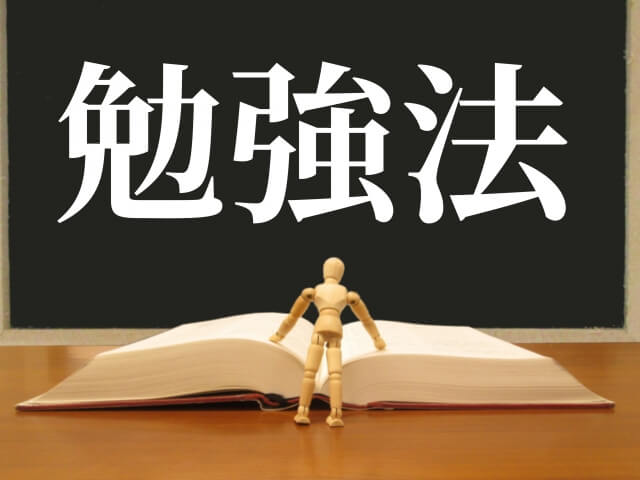
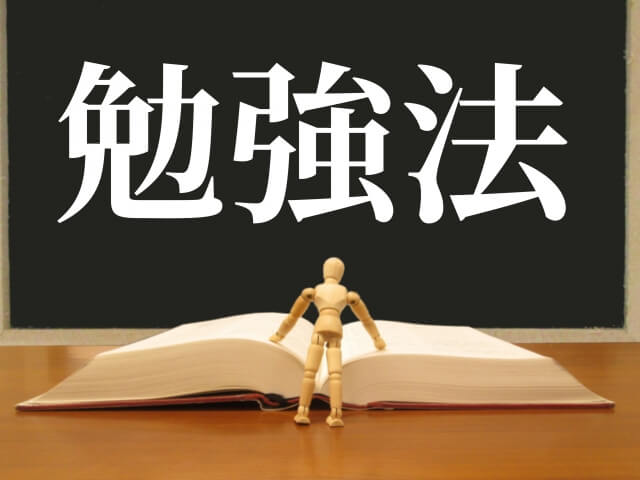
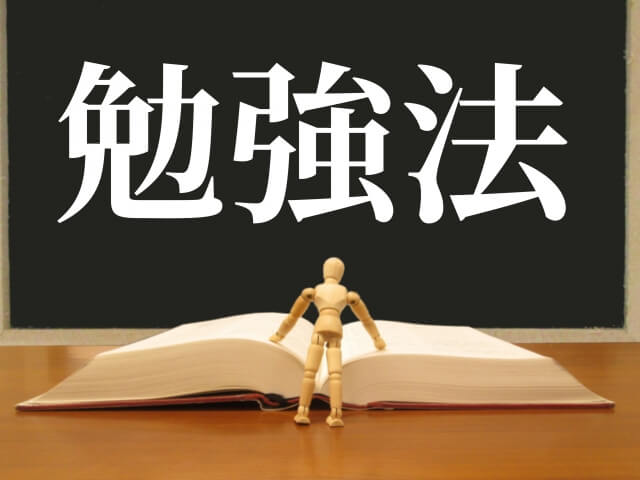
過去問の解答を作る
まず選んだ選択科目の過去問を5~10年分ダウンロードしてください。
模範解答は公表されていませんので、自分で解答を作る必要があります。
調べながら解答を作る作業を通して、出題傾向を知ることができます。
テキストを選ぶ
過去問の傾向を踏まえ、テキストを選びます。
目次を見て試験範囲をカバーできているかを確認してください。
また、難しすぎない本(大学の専門課程で最初に使うレベル)を選ぶようにしましょう。
テキストで学習する
後は選んだテキストで学習するだけです。
ただし、勉強スケジュールには要注意してください。
短答・論文(必須科目)の勉強時間との兼ね合いを考慮する必要があります。
勉強の進み具合にもよりますが、短答直前から論文(必須科目)終了までは選択科目に時間を割き過ぎない方がよいでしょう。
応用情報処理技術者試験の対策



応用情報処理技術者試験の概要
以下では、応用情報技術者試験を受験する方のための解説です(ちなみに私自身、合格しています)。
応用情報処理技術者試験の概要は次のとおりです。
| 午前 | 午後 | |
| 試験時間 | 9:30~12:00(150分) | 13:00~15:30(150分) |
| 出題形式 | 多肢選択式(四肢択一) | 記述式 |
| 出題数 | 80問 | 11問 |
| 解答数 | 80問 | 5問 |
| 合格基準 | 60% | 60% |
試験は1日かけて実施され、午前・午後の試験に分かれています。
試験範囲としては、技術分野であるテクノロジ系が6割を占めます。
その他、プロジェクト管理や情報戦略など(マネジメント系、ストラテジ系)からの出題もあります。
エンジニア職でないとピンとこない分野もありますが、試験と割り切って覚えましょう。
なお、試験は年に2回(4月、10月)実施されます。
応用情報処理技術者試験の勉強法
独学者のための勉強法
応用情報処理技術者試験のテキストで評判がよいのは次の2つです。



令和04年【春期】【秋期】 応用情報技術者 合格教本
合格教本は網羅性が非常に高いテキストですが、ITに苦手意識がある人には辛いかもしれません。
サンプルページを確認して理解できるか確かめてから購入することをおすすめします。



キタミ式イラストIT塾 応用情報技術者 令和04年
キタミ式は、イラストがふんだんに使われており、分かりやすさに定評があります。
一方、ボリュームの割に網羅性が高くないのが難点です。
続いて、アウトプット用の過去問の紹介です。



令和04年【春期】応用情報技術者 パーフェクトラーニング過去問題集 (情報処理技術者試験)
なお、午前の過去問演習は、応用情報技術者ドットコムの過去問道場で行うこともできます。
隙間時間で学習でき、間違えた問題を管理できるため、とても使いやすいサイトです。
予備校を利用した勉強法
大手予備校のLECには弁理士受験生向けの応用情報技術者試験対策講座があります。
- 情報処理をゼロから学習すること
- 選択科目以外の勉強時間を圧迫しないこと
が考慮されているので、独学に不安のある方にはおすすめです。
独学派の人であってもガイダンス動画が勉強計画に指針になると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。